皆川博子「死の泉」 ☆☆☆
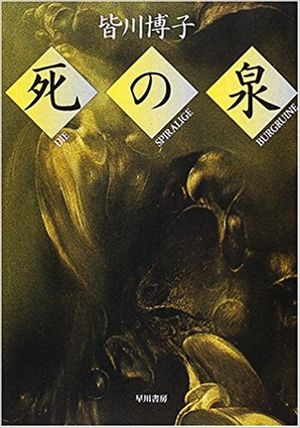
第32回(1998年)吉川英治文学賞を受賞し、1997年の「週刊文春ミステリーベスト10」で国内部門1位となった耽美的な雰囲気のミステリィです。
ギュンターなるドイツ人作家が書いた小説を日本人が翻訳した作品と言う形で描かれた、実に構成のしっかりとしたミステリィで、本当に翻訳小説を読んでいると錯覚するほど、日本人が書いたとは思えない骨格のしっかりとした海外ミステリィの雰囲気を強く感じさせる作品です。
2部構成の最初の章では、第二次世界大戦の戦火を避けてナチスの純粋アーリア人養成施設レーベンスボルンで私生児ミヒャエルを産み、マッド・サイエンテストの医師クラウスと結婚した若い女性マルガレーテの不安を描いています。
ナチス・ドイツ時代の暗い世相を背景にして、ナチと関係の深い狂気にあふれた医学者や収容施設などが描かれているため、今更ナチズムとドイツ批判を日本人が書いているのかな?という気が少ししましたが、そんなに単純な話ではなく、厳しい環境を生き抜いていくための矛盾や悲哀の様なものが全体に漂って、読み進むうちに作品の中に捕らわれてしまいます。
そして戦後14年が過ぎた第2章からはサスペンス・ミステリィの要素が強くなり、ツィゴイネル達が集うスラムの雰囲気など、何やら伝奇小説的なものを漂わせて、妖しげな青年達の登場とともに哀愁と狂気が氾濫していきます。
そして、出来すぎているけど感動的なラストの美しさを味わった後のエピローグ「あとがきにかえて」を読むと、また作品のイメージが反転してしまいます。
ともかく一筋縄ではいかない不可思議な魅力がある小説です。
